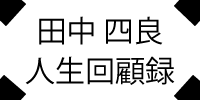私が生まれたのは昭和16年(1941年)、太平洋戦争が開戦になった年です。
大阪府の松原市で生を受けました。そこは母親の出身地で、当時、比較的裕福だった農家に産まれました。
1945年の3月からは、大阪にも東京同様空襲が行われ、悲惨だったようです。
当時、父は軍事工廠で砲弾技師をしており、日米の戦力差も明確に理解し、敗戦を予想して父の出身地である秋田県大仙市に疎開しました。私が4歳の1945年のことです。
秋田県の大仙市というのは大曲の花火で有名なところですが、冬は雪に閉ざされる豪雪地帯です。
この地で7年、小学校5年生まで過ごしました。
昭和27年、1952年、父は神奈川県藤沢市に移転します。時はまさに戦後の復興、朝鮮戦争の特需に沸き、高度成長期へと向かいます。
朝鮮特需は、朝鮮戦争に伴い、在朝鮮アメリカ軍、在日アメリカ軍から日本に発注された物資やサービス需要を指します。その額は1950年から1952年までの3年間に特需として10億ドル、1955年までの間接特需として36億ドルと言われています。
父はこの時、安全自動車株式会社という会社で軸受の製造に関わり、その後、軍隊時代の仲間と神奈川県藤沢市小塚のあたりに約1,000坪の大きな工場を持つに至ります。
この頃内閣総理大臣は池田隼人で「所得倍増論」を展開し高度成長期へと進んでいきました。


高度成長期とは実質経済成長率が年平均で10%前後を記録した1955年頃から1973年頃までを指し、名神高速道路(1963年7月開業)や東海道新幹線(1964年10月開業)といった大都市間の高速交通網、首都高速道路や阪神高速道路も整備され、都内では都営交通の地下鉄1号線(現・都営交通浅草線)、営団地下鉄(現・東京メトロ)の日比谷線といった地下鉄新線の整備が進められました。
当然、この時期に金属工業は潤い、発展していきました。
父は1961年に東洋メタル工業株式会社を設立し藤沢市小塚に軸受専門工場を建設したのです。
1961年 父が東洋メタル工業という会社を立ち上げた当時、私は20歳の大学生でした。
東京オリンピックを3年後に迎えるこのころは、戦後16年、悲惨な過去から徐々に立ち直り、反米、安保闘争の直後です。
私は学生運動には興味もなく、参加することもありませんでした。
その後、教員となり平塚学園で社会科の教師となりました。
当時の平塚学園と現在の平塚学園とではだいぶ生徒の質も違い、教師としての仕事も甘くはありませんでした。
その職場で妻と知り合い、25歳で父親となりました。
当時の私学の教員というのはあまり給与も恵まれずこのタイミング1967年に東洋メタル工業に入社、鋳込みで金属の特性などを学び、旋盤での金属加工の修業を始めました。

旋盤という機械は日常で使う身の回りのものから宇宙開発に使用される精密な部品まで、金属加工によって造られる製品はあらゆる場面で使われています。このような金属の加工に欠かせない工作機械のひとつが旋盤です。
旋盤という機械、最近の若い人は丸く削ることしか知らないかも知れませんが、ギアを取り替えることで四角でも三角にも削ることが出来ます。
今ではコンピュータ制御のNC旋盤が普及しておりますが、当時の汎用旋盤は金属加工技術の基礎を教えてくれた機械でした。
この旋盤で金属加工の基礎を学び、独学で図面の起こし方も学びました。
さらに金属の種類、特徴などあらゆることを学び、当時、東洋メタル工業で請け負っていた軸受の制作に関して、どういう金属がどんな軸受に適しているのかを習得していったのです。
1970年大阪で万国博覧会が開かれ、父親であり、代表取締役の父は全社員を万国博覧会に連れて行きました。
藤沢市内の村岡の貨物駅に臨時列車が発着し、夜行列車で大阪に世界の工業を見学しに行きました。
その当時、私は29歳です。見るものはすべて新鮮でした。
父は社内では誰にも意見を述べさせない専制君主として存在しており、逆らうものは誰もいない会社になっていました。
私が、東洋メタル工業に入社して10年、父は九州熊本に土地を求め、九州メタル工業を設立しました。(1971年創業)
当時、独裁的な経営でものを言わせない父を嫌い、私は専務として熊本で勤務しました。
当時、熊本の刑務所の受刑者に金属加工技術を講義したこともあります。懐かしい思い出です。受刑者は無期懲役などの長期刑の人が多く、彼らが出所後に会社の労働力になることはありませんでした。また、本格的な職人の技術までは身に着けられず、彼らの加工品は市場に出回ることはなく、この事業からは撤退することになりました。